KEIICHIRO SHIBUYA
音楽家・渋谷慶一郎の5枚目のソロアルバム
「ATAK019 Soundtrack for Children who won't die, Shusaku Arakawa」が発売
13 11/7 UP
photo: Kenshu Shintsubo interview & text: Tetsuya Suzuki, Madoka Hattori

- ──
- アーティストによっては自分のフィールドの中で、どれだけバリエーションを作っていくかに注力する人も多いですよね。またアカデミズムの中にギリギリ収まるような形でやる方が、ある意味合理的だったりもする。
- 「今回のサントラもいわゆる映画音楽の文法、文脈には収まっていないし、THE ENDも当たり前だけど、初音ミクカルチャーに収まっていない。収まってしまうモノに僕は興味がないんだと思います。それで言うとアーティストはもう一人一ジャンルというか、簡単に言えばキャラ立ちですよね(笑)。キャラが立っていれば、今回はファインアートです、今回はポップスです、みたいなダサイ打ち出し方をわざわざしなくていい」
- ──
- 渋谷さんは、ライバルっているんですか?
- 「ライバルがいないのが昔から悩みで、ずっと欲しいと思っているんです(笑)。これは誰なんだろう? 例えば、CMとか映画音楽の候補で僕と一緒によく名前が上がる人っていうのは知っているんですよね(笑)。でも、それは単に競合であってライバルではない。ライバルがいると三羽ガラスといわれて、取り上げられやすくなったりするから楽だし、本当はいて欲しいんだけどなぜか僕の世代は品薄ですね。あと、僕はミュージシャン同士であんまり群れたりしないからかも」


- ──
- 荒川修作や杉本博司など、アートと近しい音楽家としては池田亮司や高木正勝、若手でいえば蓮沼執太なども挙げられることもあるかと思いますが、どう見ているのですか?
- 「池田さんは真逆のタイプですよね。ずっと同じスタイルを深化させていくという。基本にパルスというかある種のビート、つまり数の概念があるところもすごく違う。高木くんは僕にとっては映像作家の割合が高くて、映像と音楽の距離がすごく近いですよね。だから僕とは映画音楽を作ってもやはり違う結果になる。蓮沼くんはアンサンブルのフィルよりも、ラップトップで作っている電子音楽のほうが面白いと思っています。『PROGRESSIVE FOrM』っていうレーベルのコンピレーションアルバムに蓮沼くんの曲が入っていて、蓮沼くんの曲が一番よかった。数を作っていない音楽家は作曲が下手なんですよね。蓮沼くんは色んな活動して数を作ってるから、出来た音楽のフォルムが自然なんです。蓮沼フィルとか文化系女子が好きなのはよく分かるんだけど(笑)、僕はああいう共感系の音楽はよくわからないからな」
- ──
- では音楽というモノを幅広くとらえ、より音楽でやれることの可能性やムーブメント、シーンが眠っているという感覚なのでしょうか?
- 「音楽を文化の一部として考えると、設定時間が全く違いますよね。音楽は短期で回収しないといけないシステムに囚われているから、衰弱していくんです。他方でアートやカルチャーを浸透、進化させるには時間がかかるし、お金や見る側の成熟も必要になってくる。そこに音楽を含めて考えるのであれば、可能性はあると思います。特に今回みたいな作品の場合、音楽業界内の競争みたいなのに加わるのは全く意味がないから配信もやらないし、先行発売はCDショップじゃなくて全国の美術館でやったりしてみたんです。こういうのは自分のレーベルというか会社だと手軽に出来るので」

- ──
- それはパッケージや流通形態にも影響してくるということですね。
- 「ジャケットは荒川修作さんの『こんにちはピカソ』(1973年)という僕が好きな、しかし彼の作品の中では決してすごく有名というわけではない作品を使わせて頂いて、インナーや裏面などで合計4点の作品を使用していたりするんだけど、体験としてこのジャケットに含まれるCDを持つということが面白ければいいわけで、あえてCDというモノにフォーカスしてみた。これは一見ナイーブに見えるけど、モノで売るということと作品性の間で出来ることは限られてるから、やってみて可能性の枠を知ればいいだけです。つまり、音楽をカルチャーやアートの枠から考えて進化させたいという人とは出来ることがあるけど、単に音楽で当てたいみたいなのは成功例なぞるだけであんまり面白いことにならないですね」
- ──
- それが、杉本博司や荒川修作といった人たちとの、映画だけでなく、いわばコラボレーションのような作り方に自然となっていったと。
- 「杉本さんと荒川さんは、モノトーンとカラフルというか、一見真逆なタイプの作家ですよね。でも僕は両者とも尊敬しています。それは、彼らの創作における肯定力なんです。『これはもうやられているからこれができない』みたいなポストモダン的な消去法の決定力ではないのが現在と相性がいいというか、現代的だなと思います」

- ──
- 映画音楽としての可能性はどのように感じていますか?
- 「これは単純な話で、映画音楽という仕事は僕が生きているうちは絶対無くならない。CDやDVDはなくなることがあっても、映画音楽という職種がなくなることはなくならないから、これから何が出来るか考えることは有意義です。映画『セイジ』のサントラを作ったときは、その前に音楽で参加した映画『告白』サントラのコンピレーション的な作り方を見て、これのエレクトロニカ版が出来るなと思ってプロデュースしたりした。杉本さんと荒川さんのほうは、僕自身のソロアルバムに近づけてみたりした。映画音楽というフレームもオペラと同じように、古典的な枠組みだからこそ書き換えられる面白さがあると思います」
- ──
- 自分自身のアイデンティティを、スタイルでも器でもない、変化していくことでより強めていく。今回の作品はよりピュアで、渋谷慶一郎らしさが素直にでているのかなと。単純に聴きやすいということもありますよね。
- 「そう、僕は変化が好きです。普遍性みたいなものに意味があるとしたら、変化していく中で残っているものだからなわけで、普遍性そのものを目指したりするのは筋違いというか勘違いですよね(笑)。今回の『ATAK019』のようにある程度フリーフォームで自分が好きなように音を出している作品で大事なのは聴けないといけないことです。第一次情報として、まず耳に残らないといけない。その奥に色々なレイヤーがあって何度聴いても発見がある、という。そこはかなり気を使いました。このアルバムでいわゆるレコ発イベントみたいなのをするのは難しいかなと思うし、今どきレコ発っていうのもどうかと思うので(笑)、THE ENDのパリ公演後、年末に東京で久しぶりのソロ・コンサートを予定しています」
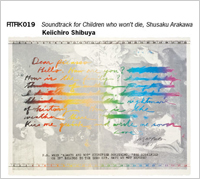
ATAK019
Soundtrack for Children who won't die, Shusaku Arakawa
2,400円[税込]
製品番号:ATAK019
発売元:アタック・トーキョー株式会社
http://atak.jp/data/atak019
amazon


