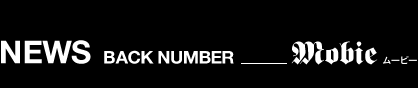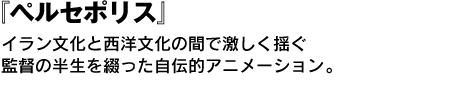
間違いなくイランは世界有数の映画大国である。リアルさと詩的な要素を巧みにブレンドし、映像によって世界を思考する、という方法論がこれほど確立されている国はないだろう。もっともそれは「言いたいことが何でも言える国ではない」から発達したものでもある。現に日本で劇場公開(あるいは映画祭公開)されたものでも、本国では上映禁止なままの作品がいかに多いことか! なぜならイランはイスラーム原理主義国家であるからだ。そのおおもとが1979年のイスラーム革命(俗にいうホメイニ革命)にあるのは間違いない。
現代でも革命を貶めることは絶対的タブーであるイランだが、この『ペルセポリス』の原作・脚本・監督はパリ在住のイラン人女性グラフィック・ノヴェリスト、マルジャン・サトラビ。テヘランの知識人階級の家に生まれた彼女は、10歳のときに革命を体験。代々リベラルな家風ではあったが、共産主義者であった叔父も王政が倒れたので獄中から解放され、彼が大好きな幼いマルジェは盲目的に大喜び。しかしそうした“自由”な時は一瞬にして過ぎ去り、宗教国家的色彩を濃厚にしはじめたイランは以前にも増して恐怖政治化していく。さらに翌年のイラン・イラク戦争の勃発から極端な反動化がはじまって……。
といって、これは単にイスラーム革命を批判する作品ではない(もちろんイラン国内では絶対に上映不可能だが)。「革命の蜜月期」が儚い夢であることはロシア革命以来誰もがよく知るところだからだ。アメリカ文化に憧れ、ブルース・リーをヒーローと崇め、ロンドンのパンクスに共鳴するような主人公マルジャンは、イラン国内の風潮を危惧した父母によってウィーンへと留学させられてしまうが…… そこから彼女は恋に落ちたり結婚したり、はたまたホームレス生活にまで堕ちながらも、イラン文化と西欧文化のあいだで激しい揺らぎを繰り返していく。これがもう、少女のアイデンティティ確立の物語として最高の面白さ! 過酷な現実を裸で描いているのに常に自嘲的ともいえるユーモアが漂うのがなにより素晴らしい。はっきりと自伝であるのにここまで醒めているというのも、この作家の知性を物語っている。
とまあ、題材が題材だけに見過ごされがちだが、この作品の最大の美点は終始、黒と白だけで貫かれたアニメーションであるということだ(というのは嘘で、現代のパートはカラーなのだが、これがまた儚い)。簡素かつグラフィックなヴィジュアルで、語るべきことのすべてを表現する手法はアニメーションの新しい地平を拓いたといっても過言ではない。
ま、これはフランス映画であるから、カトリーヌ・ドヌーヴ&キアラ・マストロヤンニ母子らによるフランス語が使われてはいるものの、作者のルーツ たるイランの「映像で思考する」という美質を想起させずにはおかない。なにより素晴らしいのがマルジャンの祖母! 下ネタ上等、思ったことを遠慮会釈せず、ウィッティな言葉で言ってのける自由闊達な精神こそが本来のイラン=ペルシャ文化 (「ペルセポリス」とは古代ペルシャ国家の謂である)なのだと、このキャラクターこそが体現しているようだ。
Text:Milkman Saito
『ペルセポリス』
原作・監督・脚本 : マルジャン・サトラピ
共同監督・共同脚本:ヴァンサン・パロノー
原題:PERSEPOLIS
2007年/フランス
上映時間:1時間35分
提供:ロングライド/アスミック・エース エンタテインメント
宣伝:樂舎
配給:ロングライド
12月22日(土)より シネマライズほか全国順次ロードショー
© 2007. 247 Films, France 3 Cine´ma. All rights reserved.