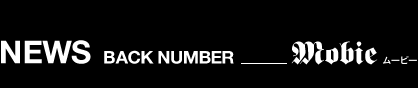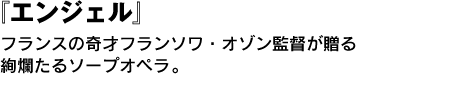
出てくるヤツは俗物ばっか。その頂点が主人公のバカ女…その名もエンジェル、という作品だけど(笑)、なぜかさほど嫌悪もさせず、かといって感情移入もさせずに波瀾万丈(でも型通り)のメロドラマをやってのける。しかも20世紀初頭のイギリスを舞台にしたコスチューム・プレイ、当然全編英語であるが、監督はあのフランスの奇才フランソワ・オゾン。もちろん彼にとっては初の英語劇だが、そのことによる不自然さはまったく感じさせない出来。絢爛たるソープオペラに仕上がっているのだ。そう、ソープオペラこそ、出世作『ホームドラマ』('98)以来のオゾンのお得意技ではないか。
騎士道物語にうつつを抜かしたドン・キホーテよろしく、上流階級の暮らしに普通じゃない憧れを抱く16歳の労働者階級の娘エンジェル。ドン・キホーテと違って読書経験皆無にもかかわらず妄想パワーで物語を紡ぎだし、歯の浮くようなロマンス小説を書いて自信たっぷりに売り込んだ。それがなんと数奇者の出版社主(サム・ニール)の目に留まり、「シャンパンをコルクスクリューで抜く」などという噴飯モノの描写満載にもかかわらずベストセラーに! エンジェルは大成功、崇拝者まで現れ、憧れの大豪邸も買収し……しかしロマンス的生活を望んだエンジェルの行く末に、非ロマンス的な人生が待っていようとは(ってあたりまえだ)。
この物語で唯一俗物的でないのは出版社主の妻ハーマイオニー(シャーロット・ランプリング)。“ベストセラー小説”をせせら笑う常識を持ち、無教養で傲慢なエンジェルに血道をあげる夫を冷静に眺めている。しかしまたハーマイオニーだけが「悪趣味だけどすべてを自分の力で手に入れたたいした女だ」とエンジェルのことを的確に認めてもいるのだ。おそらくこれがオゾンのエンジェル観。まあ、主人公を可愛いと思えるかどうかは観客それぞれであるけれど(笑)、こうしたメロドラマ趣味を否定するのもまた“文学的”ではないだろうしな。ましてや“映画的”ではないよね。
筆者にとってオゾンは、作品によって好き嫌いの大きく分かれる監督。例えば前作『ぼくを葬る』などはどこが感動的なのかてんで判らないのだけれど(笑)、これはキッチュな疑似テクニカラーをはじめ50年代ハリウッド映画のパロディじみた『8人の女たち』の系譜。意地の悪さも、妙な本気度も、まるで名古屋制作の昼ドラみたいだが、まあケイタイ小説とその映画化全盛のご時世、あんがい笑って済ませちゃいけないものかも知れないな。
Text:Milkman Saito
『エンジェル』
監督・脚本 : フランソワ・オゾン
ダイアローグ:フランソワ・オゾン、マーティン・クリンプ
原作:エリザベス・テイラー
製作総指揮:ターニャ・セガーチェン
製作:オリヴィエ・デルボス、マルク・ミソニエ
出演:ロモーラ・ガライ、シャーロット・ランプリング、
ルーシー・ラッセル、サム・ニール、ミヒャエル・ファスベンダー他
2007年/フランス、ベルギー、イギリス
原題:Angel
上映時間:119分
配給:ショウゲート
12月8日(土)、日比谷シャンテシネ、新宿武蔵野館他、全国ロードショー
© 2006 - Fidelite Films - Headforce 2 - Scope Pictures - FOZ - Virtual films - Wild Bunch - France 2 Cinema