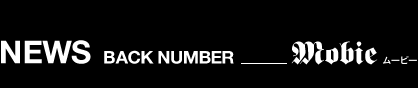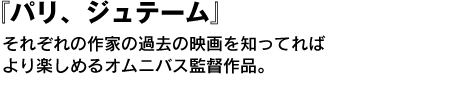
オムニバスはとにかく個性こそが勝負だ。自分らしさを一瞬で提示できないとどうしようもない。
とりわけ2時間のうちに18監督が競作するという本作のような場合、より瞬発力が求められるのは当然だ。パリの各地区を舞台にちいさな恋物語を紡いだものだが、その点、それぞれ独自の戦略を練ってかなりの打率でヒットを飛ばしているのはお見事というしかない(もちろん凡退に終わったヤツもあるけれど)。
目ぼしいものを順番に挙げよう。まずはイギリスのインド人女性監督グリンダ・チャーダ。セーヌ河岸でナンパしてる青年とヘジャブ(スカーフ)をしたイスラーム少女の物語だが、それぞれの民族・宗教的アイデンティティを大事にしようという『ベッカムに恋して』に繋がるテーマがよく出ている。それに、さすがキーラ・ナイトレイを見いだしたチャーダ、少女の審美眼は抜群(笑)。
息子を亡くした母親(ジュリエット・ビノシュ)が、哀しみを吹っ切るまでをスケッチした諏訪敦彦作品は白眉。夜の無人のヴィクトワール広場に、大きな馬に乗ったカウボーイ(ウィレム・デフォー)が現れるショットは映画の魔力が横溢している。
『ベルヴィル・ランデブー』のアニメ作家シルヴァン・ショメは実写を撮っても凄い。パントマイム男が恋を見つけるまでを描いたノスタルジックでテクニカル、それでいて詩的リアリスムに溢れた傑作。
『ラン・ローラ・ラン』、新作『パフューム』のトム・ティクヴァは、駆け出し女優ナタリー・ポートマンと盲目の学生との物語。これがまた上映時間は短いが、おそるべき分量の時間をコマ撮りで処理し、まさに「時が飛ぶように過ぎる」さまを表現するというもの。同じセンテンスを繰り返しつつ、恋心の変化を表現するのも巧い。
俳優ジェラール・ドパルデューが自ら監督・出演した一篇は、彼のジョン・カサヴェテスへのオマージュだけでできたようなもの。なんせカサヴェテス映画の象徴、ジーナ・ローランズとベン・ギャザラが、腐れ縁夫婦に扮してドパルデューのカフェで再会するのだ!
トリを務めるアレクサンダー・ペインもまた素晴らしい。パリにひとりでやってきたデンヴァーの郵便配達おばさんのモノローグだけで構成された作品だが、『アバウト・シュミット』を彷彿とさせる孤独感と「生」の実感が沁みいるように心に届く。
他にも、コーエン兄弟、ウォルター・サレス、アルフォンソ・クアロン、ヴィンチェンゾ・ナタリ、ウェス・クレイヴンあたりがとても楽しい出来。それぞれの作家の過去の映画を知ってればより楽しめるのはもちろんなのですが。
Text:Milkman Saito
『パリ、ジュテーム』
監督:ジョエル・コーエン、イーサン・コーエン、オリヴィエ・アサイヤス、諏訪敦彦、ガス・ヴァン・サント、トム・ティクヴァ、ウォルター・サレス、アレクサンダー・ペイン、アルフォンソ・キュアロン、クリストファー・ドイル、ウェス・クレイヴン、グリンダ・チャーダ、シルヴァン・ショメ、イザベル・コヘット、ジェラール・ドパルデュー、リチャード・ラグラヴェネーズ、ヴィンチェンゾ・ナタリ、ダニエラ・トマス、オリヴァー・シュミッツ、フレデリック・オービュルタン
出演:ナタリー・ポートマン、ジュリエット・ビノシュ、ファニー・アルダン、イライジャ・ウッド、マギー・ギレンホール、スティーブ・ブシェミ、メルキオール・ベスロン、ギャスパー・ウリエル、イライアス・マッコネル、マリアンヌ・フェイスフルほか
2006年/フランス
上映時間:2時間
配給:東宝東和
(c) Mathilde BONNEFOY / Victoires International 2006
3月3日よりシャンテシネ、恵比寿ガーデンシネマ、新宿武蔵野館、川崎チネチッタほか、全国順次ロードショー