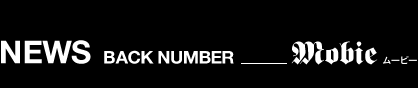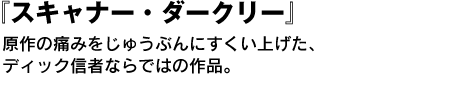
おお。ようやくディック小説の完全映画化(というか本質的な映画化)といっていいものが生まれたって印象だ。ハヤカワ文庫でフィリップ・K・ディックの面白さにハマって絶版本を探し、『ブレードランナー』も初日に劇場へ走り、サンリオSF文庫の翻訳は出るたびに即購入していた僕としてはやはり感慨深いものがある。しかもディック作品の中でも飛び抜けてリアルで沈痛な、あの「暗闇のスキャナー」が原作。しかも驚くほど忠実なのだ。
どこがディック的かといって、麻薬常用者たちがラリった頭で、買ってきた自転車のギアの数についてどうでもいい議論を白熱させるシーン。これをディック的といわずして何というか。摘発すべき麻薬物質「D」にいつしか耽溺した囮捜査官(キアヌ・リーヴス)が自分自身を監視することになり、ゆるやかにカタストロフへと堕ちていく……このアイデンティティ崩壊感覚こそディックである。
ただこの作品、俳優を使って撮った映像を全編サイケデリックなアニメーション手法でトレースしている。監督リチャード・リンクレイターがかつて『ウェイキング・ライフ』で試みたものと同じだが(そこでもディックについて言及されていた)、これが僕には映像表現としての「逃げ」にいささか見えぬでもない。作品唯一のSF的ガジェットといえるスクランブル・スーツ(瞬間的に実像が変容して、着ている者の個体識別を不可能にする服)の描写にはなるほどこれしか、と思わせるが、生身の俳優たちのせっかくの快演までをも客体視させすぎるのは事実である。
それでも本作は原作の痛みをじゅうぶんにすくい上げた、ディック信者ならではの作品ということができる。ラストで流れる麻薬による死者たちへの献辞にも、原作読了時に感じたのと同様の、存在への深い哀しみをやはり感じてしまうのだ。
Text:Milkman Saito
『スキャナー・ダークリー』
監督:リチャード・リンクレイター
出演:キアヌ・リーヴス、ロバート・ダウニー・Jr、ウディ・ハレルソン、ウィノナ・ライダー、ロリー・コクレインほか
2006年/アメリカ
上映時間:1時間40分
配給:ワーナー・ブラザース映画
シネセゾン渋谷にてロードショー中