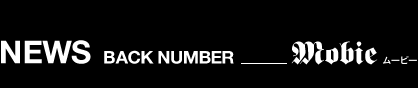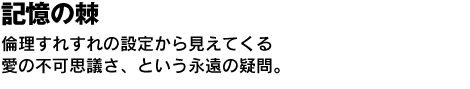
ジャミロクワイ、レディオヘッド、ブラー等のPVで、MTV界では誰も知らぬ者のないジョナサン・グレイザー監督の長編映画である。ロンドン生まれの彼だけあって、NYの話なのに全編ヨーロピアンな、半ば頽廃的ムード漂うシックな映像。冒頭、ジョギングする男の後ろ姿を延々と追うキャメラと、いささかワーグナー的あるいはリヒャルト・シュトラウス的なアレクサンドル・デプラのオーケストラが同調していくシーンはじめ、滑らかなヴィジュアルと音楽の融合もさすがである。
しかしこれは、なんといっても脚本家ジャン=クロード・カリエールの映画なのだ。カリエールといえば、ジャック・タチの弟子であり、映画史最大のシュルレアリスト、ルイス・ブニュエルの後期作品におけるパートナー。突飛な状況を日常の中に投げ入れて異化させることにかけては並ぶもののない猛者なのである。
主人公は10年前に夫を亡くしたハイソな未亡人(ニコール・キッドマン。スターのくせに変な映画に続々出るなぁ)。ようやく新しいパートナーと新生活を始めようとした矢先、いきなり10歳の少年が現れて断言するのだ。「僕は君の夫だ。生まれ変わりなんだ」……。
こうした倫理すれすれの設定は、チンパンジーと三角関係になる外交官一家の物語『マックス、モン・アムール』('86、大島渚監督!)でも用いられていたが、まるで姉妹編のような本作でもニコールと少年はかなり際どいところまで進んでみせる。もっともオチはまったくもって人を食った物凄いモノだけど(笑)、リアリストを超えたリアリストであるカリエールとしては当然か。「転生」への見解は劇中でひとり超然と醒めたローレン・バコールの態度に顕れているが、その向こうに見えてくるのは愛の不可思議さ、なにをもって愛と呼ぶのかという永遠に解決の出ない疑問なのだ。
『記憶の棘』
監督:ジョナサン・グレイザー
脚本:ジャン=クロード・カリエール、マイロ・アディカ、ジョナサン・グレイザー
出演:ニコール・キッドマン 、キャメロン・ブライト 、ダニー・ヒューストン 、ローレン・バコール 、アリソン・エリオットほか
2004年/アメリカ
上映時間:1時間40分
配給:東芝エンタテインメント
2006年9月23日(土・祝)より日比谷シャンテシネ、新宿武蔵野館ほかにて全国ロードショー!
http://www.kiokunotoge.jp/