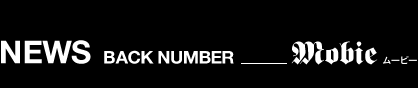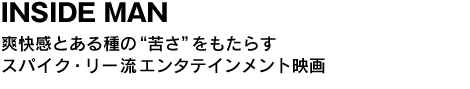
ひとことで言って、これはとりあえず「銀行強盗映画」である。銀行に押し入った犯人たちと盗みの手口、巻き込まれた銀行員や客たちの反応、取材に押しかけるマスコミたち、といった「お約束」は本作でもきっちり守られていて、それ自体とてもスリリング。最上級のサスペンスといってもいい。しかし犯人たちの計画が明らかになっていくにつれ、この強盗行為そのものがまったく別の様相を帯びてくるのだ。
ストーリーは4つの視点が交錯するなかで進んでいく。終始顔を覆面で覆った強盗団(リーダーはクライヴ・オーウェン)。NY警察の刑事でネゴシエイターとなるデンゼル・ワシントン。襲われる銀行の会長クリストファー・プラマー(かつて銀行強盗モノの傑作『サイレント・パートナー』に出てたな)。そして彼に事件の鍵となる秘密を示唆されて、現場に介入してくる腕利き弁護士ジョディ・フォスター。
やがて判明する、銀行強盗の「本当の理由」は観てのお楽しみとしておこう。しかしただ単なるあっけないオチではなく、現代社会にはびこる暴力連鎖、過去の歴史の痛みというものを強烈に意識させるもので、爽快感いっぱいではあるものの、ある種の苦さも観客にもたらすのがいい。
監督はおそらく本作が初の正面切ったエンタテインメント映画となるスパイク・リー。とっくにブラック・シネマの範疇を飛び越え、アメリカ映画屈指の演出力を誇る彼であるが、前作『25時』('02)で真っ向からアプローチした9.11へのメッセージをここでも潜ませているのは間違いない。人質となったシーク教徒がアラブ人と間違われたり、やはり人質となった少年が犯人の行動よりもよほど血なまぐさい暴力ゲームにハマっていたり、さらにテーマ曲には、タミル映画の巨匠マニ・ラトナムがインド/パキスタン紛争を描いた『ディル・セ 心から』('98)の挿入曲を選んだりと、スパイクの仕組んだ目配せはかなり細かいのである。
監督:スパイク・リー
出演:デンゼル・ワシントン、クライヴ・オーウェン、ジョディ・フォスター、ウィレム・デフォー、キウェテル・イジョフォーほか
2006年/アメリカ
上映時間:2時間8分
http://www.insideman.jp/
配給:UIP映画
みゆき座ほか全国ロードショー中