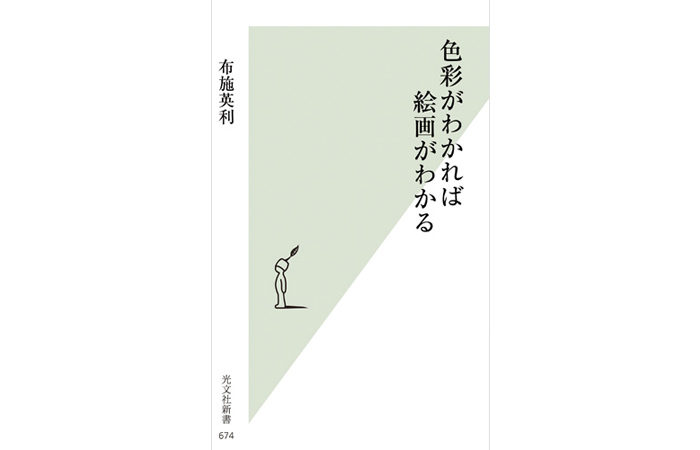
「色彩がわかれば絵画がわかる」
「色」とは何なのか。「色彩学」の基本理論から色と絵画の関係性を紐解く一冊。
14 3/11 UPDATE
きわめて平易な語り口で、色彩学の基礎を紐解いてくれるのが本書だ。とはいえ、その「色彩学」というものが、この日本で、どの程度の厚みでもって研究され、教育されているものやら、僕には皆目検討がつかない。かれこれ20年近く、僕は仕事の一部として、グラフィック・デザインやエディトリアル・デザインをおこなってきた。しかし専門教育は受けたことがない。独学ですらない。Macの前で「習うより慣れて」いって、今日にまで至った。であるから、たとえば美大の学生が日々なにを学んでいるのか、まったくよくわかってはいない......という僕みたいな人こそ、本書は手に取るべき一冊だろう。
冒頭、まずは「三原色」について語られる。「赤」「青」「黄」、あるいは、「赤」「青」「緑」の三原色は、それぞれ「なぜその組み合わせなのか?」が解説されていく。色彩学の基礎を作ったニュートンの「七色」説から、19世紀の物理学者ヤングによる「三原色」説へと進み、混色から中間色、補色それぞれの意味が語られて、フォトショップ使いにはお馴染みの「色相・明度・彩度」とはなにか?が解かれたならば、つぎはマンセルの色立体......と、進んでいって、四原色説から「進出色と後退色」、色の遠近法から膨張色と収縮色、色温度、そして「それらの理論すべてを踏まえて初めて、『その技法の効果』をより正確に、より効果的に咀嚼することができる」名画の構造が分析されていく。たとえば、ゴッホの『鳥がいる麦畑』、ラファエロの『アテネの学堂』、そしてダ・ヴィンチの『最後の晩餐』――これらがすべて、愚直なまでに「色彩の理論」にしたがった絵画であることが、名探偵の謎解きのごとく明かされる。そして読者は知ることになる。人類史に残るこれらの名画とは、まず第一義的には「天才的な芸術家が自らの魂を塗り込んだもの」である、のかもしれない。しかしその一方で、まるで科学者が実験をするかのように、「色彩の理論」を実践で証明してみせるための各種の挑戦でもあった、ということを。
つねづね僕は疑問に思うのだが、こと日本においては、芸術にかんする事柄を科学的に分析・研究していくという姿勢がいつになっても定まらないのはなぜか、ということだ。だからもしかしたら、本書で「一般向け」にやわらかく噛み砕かれている各種の理論すら、専門教育機関においては「あまり重視されていない」オルタナティヴな言説も含まれているのかもしれない(が、僕にはわからない)。そういった意味も含めて、僕のようなDIY・パイレート・デザイナーだったら、本書から得るところは多いはずだ。イッテンの色相環とその理念をかじるだけで、その後の作業速度に大いに影響することは間違いない。また、随所に出てくる、ゲーテによる色彩と人の感覚との共振への考察、とくにその「調和」理論は興味ぶかい。アートと音楽と文学が収束していく一点が指し示されているようですらある。そういえば、ピンク・フロイド『ザ・ダーク・サイド・オブ・ムーン』の、ヒプノシスによるジャケット・デザインの元ネタも、ゲーテによる光スペクトルを図案化したものだったことも思い出す。
言い忘れていたが、本書は新書ではあるが、随所にカラー図版が豊富に盛り込まれている。「参考書」としての実用性を重視した意識のあらわれとして、こんなところも好感度が高い。
text: DAISUKE KAWASAKI (Beikoku-Ongaku)
「色彩がわかれば絵画がわかる」
布施英利 著
900円[税抜]
(光文社新書)



