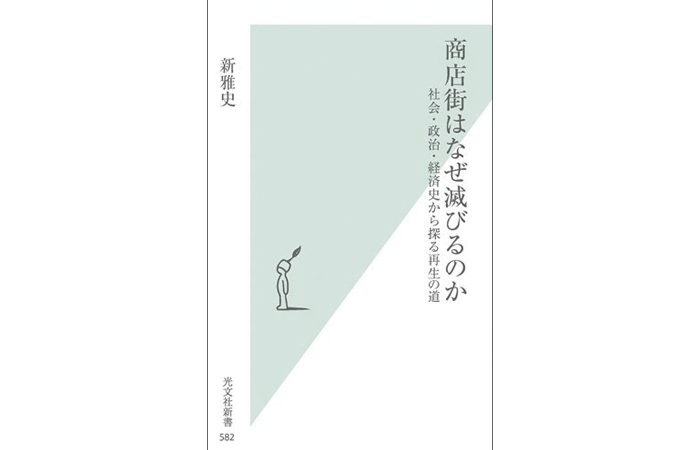
商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道
「きわめて人工的に」生み出された特殊な日本の商店街、その成立過程と内実に迫る一冊。
12 10/23 UPDATE
今日我々が目にする商店街は、「ずっと昔から」自然に出来上がったものではない。20世紀になってから「きわめて人工的に」生み出されたものなのだ――という歴史の盲点を掘り起こして提示したことで、ちょっとしたセンセーションを巻き起こしているのが本書だ。目から鱗が落ちる人もいるかもしれない。
まず、本書がはっきりと示すのは「日本のような商店街」は日本にしかない、という事実だ。どうも日本人は、パリのパサージュや、アラブのスークや、あるいはアメリカのモールなどと日本の商店街との共通点を探る、といった方向性の論考がなぜかことのほか好きなようなのだが、本書がやったことは、そのまったく逆だ。日本の商店街は、いかなる外国の商業施設や商店街とも「似てはいない」。それどころか、根本的な「理念」のレベルで、なんの関係もない。ここから話は始まる。
どこの駅前にもかならずある商店街、というものは、日本にしかない。あるいは、ターミナル駅の周辺などに特徴的な、あたかも街全体がひとつの商圏を複合的に形づくっているかのようなメガ商店街なども、日本にしかない。ではなぜ、それが「日本だけ」なのか? 本書はそこを掘り下げる。見えてくるのは、かぎりなく苦い現実だ。日本がすでに「近代化することに失敗してしまった」という現実がそれだ。「特殊な商店街」を持つ「特殊な近代国家もどき」こそが日本だった、ということだ。
日本の商店街が、現在のものと近しい形にまで整えられたのは、1930年代だったそうだ。百貨店のほうが先に成立をしていて、それに対抗するため「急いで体勢をととのえた」のが近代的な商店街だった――ということを、僕はこの本で初めて知った。そして、全体主義国家と化していく当時の世相のなかで、あたかも国家総動員法に準じるかのように「いろいろな規制」のもと整備されたショッピング・ゾーンとしての商店街が発展していく。ここの「規制」というのがミソで、のちの大店法にまでつながっていく。商店は家族経営が多く、それら商店がまとまって組合を作り、それが保守政党の支持母体ともなっていく......ホワイトカラー中心史観のなかでは、守旧派としてつねに蔑視されうる「ザ・地元」の典型例のひとつとしての商店街、その成立過程と内実のおおよそのところが、コンパクトに紹介されていく。本書の読みどころは、まずここだろう。
そして、そうした「日本の商店街」は、その特殊性ゆえ、滅びの道を歩んでいくことになる。あらゆる規制緩和はもとより、後継者難、人口減、あるいは、新自由主義的政策のもとで「一般的ホワイトカラー層」こそが、最も急進的な右派として肥大化していったこと、これも関係していたのかもしれない。「どこにでもある」はずの商店街は、いまや風前の灯火であり、コンビニやファストフードのフランチャイズ店が残るだけで、あとは借り手のいない貸しビルと開かないシャッターが並ぶことになるのだろう......と、こうした悲惨な未来に対抗して、著者は本書後半で「再生の道」を示そうともしているのだが、ここはあまりパッとしない。本書にて「商店街再生のアイデア」を得たいと考えている人にとっては、この点、大いに不満が残るのではないか。
しかし、それはそれでしょうがない、と僕は思う。「再生のアイデア」がろくすっぽ出ないようなところまで、「商店街という理念の限界」を考えぬいた、著者の生真面目さをこそ僕は評価したい。おためごかしな「再生のアイデア」とやらが、いったいどれほどの回数、日本のありとあらゆるものを根本的に粉砕破壊したことか。きらびやかな「アイデア」など、ぜんぶ詐欺に決まっている。なにより、現在進行形の詐欺であるTPPと消費税が、商店街のすべてを平らげてしまうだろう。昨年12月、僕は本欄で、アメリカと日本政府によりこの先進められるだろう『ショック・ドクトリン』について書いた。いまのところ、すべてそのとおりになっている。であるから、商店街は終わるのだろう。「商店街がある日常」に慣れきっていた、およそここ100年近くのあいだつづいた日本人の生活というものも終わるのだろう。
著者は、北九州の商店街の酒屋に生まれ育ったそうだ。その子供時代を振り返った「あとがき」がすさまじい。我々がなくしてしまって、もう取り返しがつかないものとはなにか。その一端が、誠実なる苦悶の果てに、本書のなかに刻印されている。
text: Daisuke Kawasaki (Beikoku-Ongaku)
「商店街はなぜ滅びるのか 社会・政治・経済史から探る再生の道」
新雅史・著
(光文社新書)
777円[税込]



